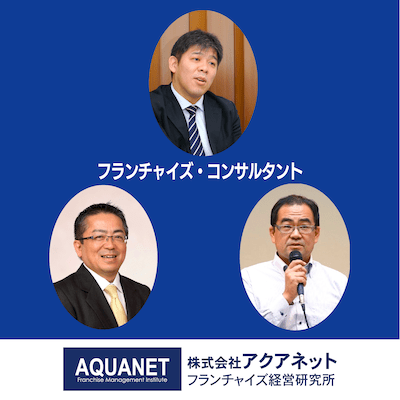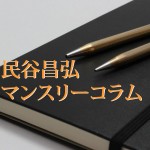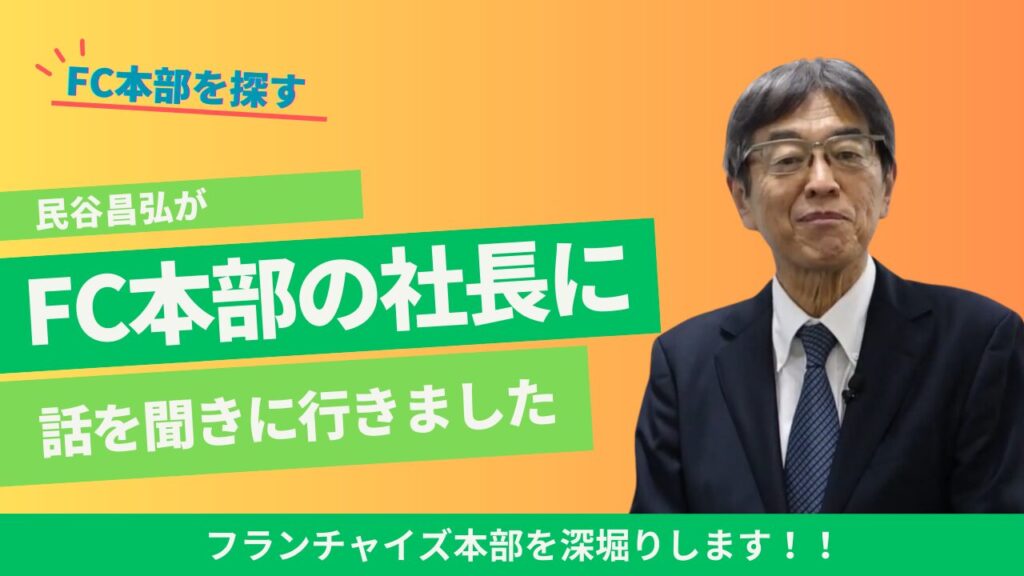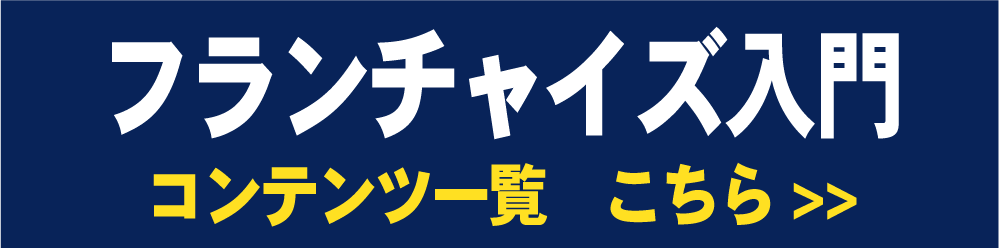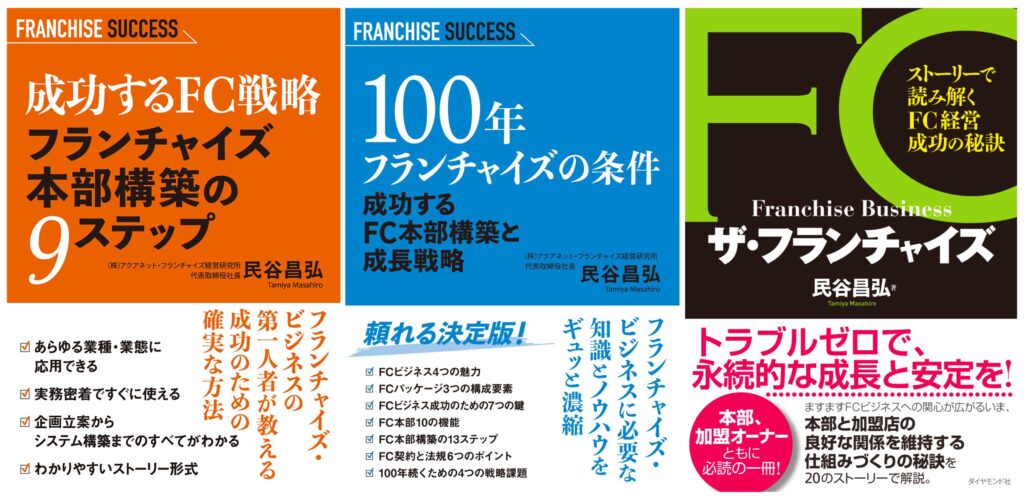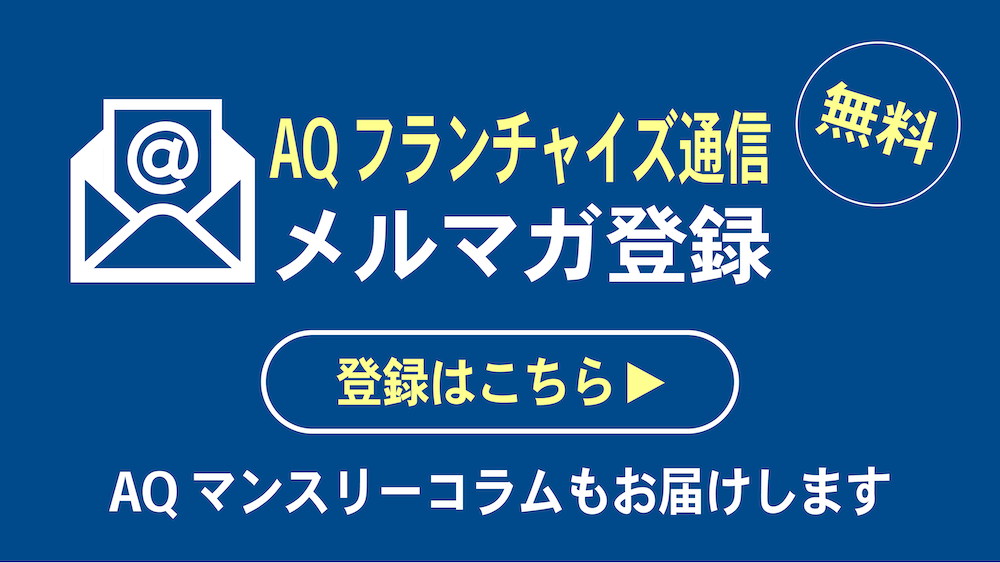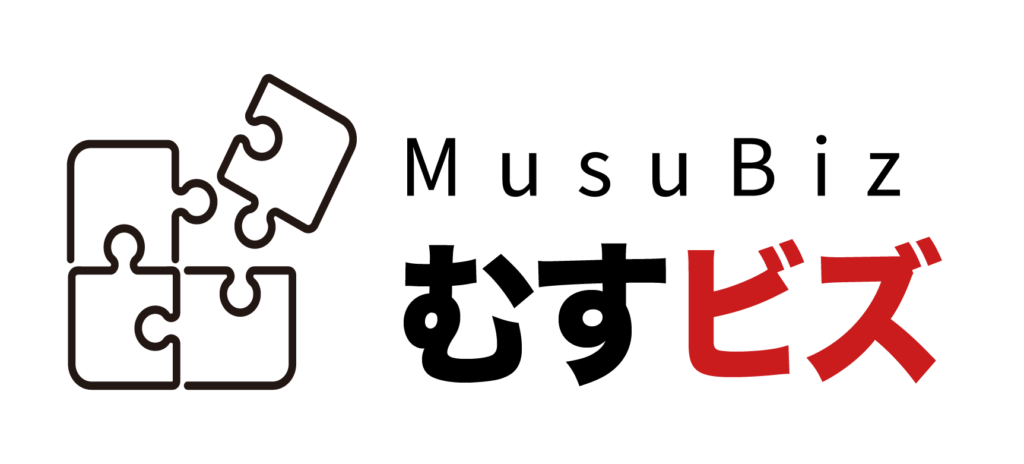加盟店の成長を支援するはずの本部自身が、「人が育たない」「引き継ぎがうまくいかない」と悩んでいるケースは少なくありません。
現場の人材不足だけでなく、本部の中で“業務の属人化”が起きていることが、その背景にあることも多いように思います。
「教えにくい」「任せにくい」は、属人化のサイン
本部での育成スタイルは、意外と“場当たり的”になっていないでしょうか?
「この仕事は慣れれば分かるから」
「まずは一緒にやってみて」
といった、口頭とOJTだけに頼ったやり方では、教える側にも負担がかかり、教えられる側も業務の全体像をつかみにくくなります。
結果として、業務は“その人でないと回らない”状態になり、誰かが退職したり異動したりした際に、ゼロからの立て直しが必要になります。
引き継げる組織は、「共通のやり方」がある組織
業務が引き継げる組織には、決まった“言い方”と“やり方”があります。
*誰がやっても同じ結果になるフォーマット
*過去のやり取りや判断が残っていて参照できる体制
*社内用語や判断のルールが統一されている状態
こうした仕組みがあると、「属人的な経験」ではなく「再現できる行動」として業務を引き継げます。
これは単に新人を教えるためだけでなく、SVや企画スタッフ同士が横断的に業務を受け渡す際にも、非常に大きな価値を持ちます。
“書く”のが苦手でも大丈夫——生成AIで言語化をサポート
「マニュアルを書こうと思っても時間がない」
「どう表現すればよいか分からない」
——そう感じる方も多いと思います。
そこでおすすめしたいのが、生成AIを業務の“書き起こしパートナー”として使うことです。
たとえば、
自分のメモや箇条書きを、AIに文章に整えてもらう
「この手順を5ステップにまとめて」と依頼して、たたき台を作ってもらう
過去の社内Q&Aを整理し、“社内FAQ”としてまとめる
こうした活用は、個人レベルで始められる小さな工夫です。
AIは専門的な知識やシステム導入がなくても使えます。
まずは“1業務、1ドキュメント”からでも始めてみると効果を実感しやすいでしょう。
■育成を支えるのは、「引き継げるか?」の視点
業務の棚卸しを進めると、日々の小さな業務の中にも「誰か1人に頼っている」業務が多く見つかります。
そこで必要なのが、「この仕事、明日から他の誰かが対応しても大丈夫だろうか?」という視点です。
*手順は明文化されているか
*担当変更後でも困らない情報が共有されているか
*実際に他の人がやってみて、スムーズに回るか
この視点で日常業務を見直すことが、「引き継げる」「育てられる」本部をつくる土台になります。
■小さな仕組みが、強い本部を支える
*ファイル名のルールを揃える。
*テンプレートを整える。
*マニュアルを少しずつ書き加える。
*そして、AIにも少しだけ手伝ってもらう。
そんな地道な取り組みが、結果的に本部機能の安定性を高めます。
属人化した業務は手放しづらく、結果的に“育成できない組織”になってしまうリスクもあります。
今、自分が担当している業務は、明日別の誰かに渡せる状態になっているか?
その問いから、次の一歩が見えてくるはずです。